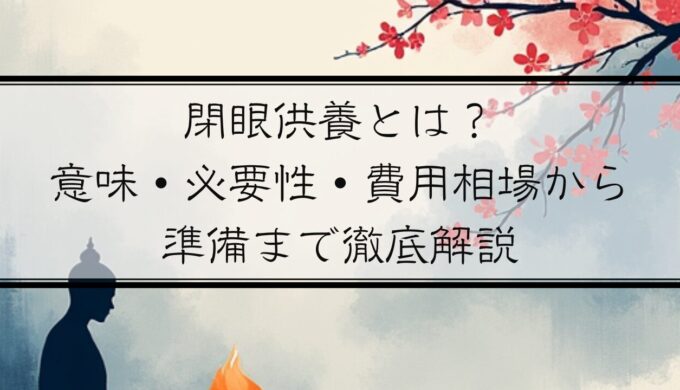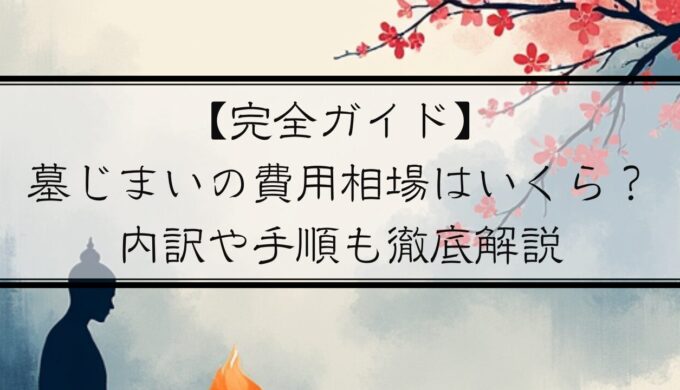寺院墓地にあるお墓を撤去し、檀家をやめる「離檀」を考える際、多くの方が気になるのが「離檀料」です。
「いくら支払うべきか」「そもそも支払う義務はあるのか」と疑問をお持ちの方も多いでしょう。
この記事では、離檀料の基本から相場、支払い義務の有無、さらには最新の供養サービスまで、詳しく解説します。墓じまいや改葬を検討されている方はぜひ参考にしてください。
離檀料とは何か?お寺との関係を円満に終える感謝の印
「離檀(りだん)」とは、檀家をやめることを指し、特定の寺院との契約を解消することです。
そして「離檀料」とは、これまでお世話になった寺院への感謝の気持ちを示すためのお布施の一種です。
離檀の際には、寺院墓地にあるお墓を撤去し、その区画を寺院に返還する必要があります。この過程で発生するのが離檀料です。
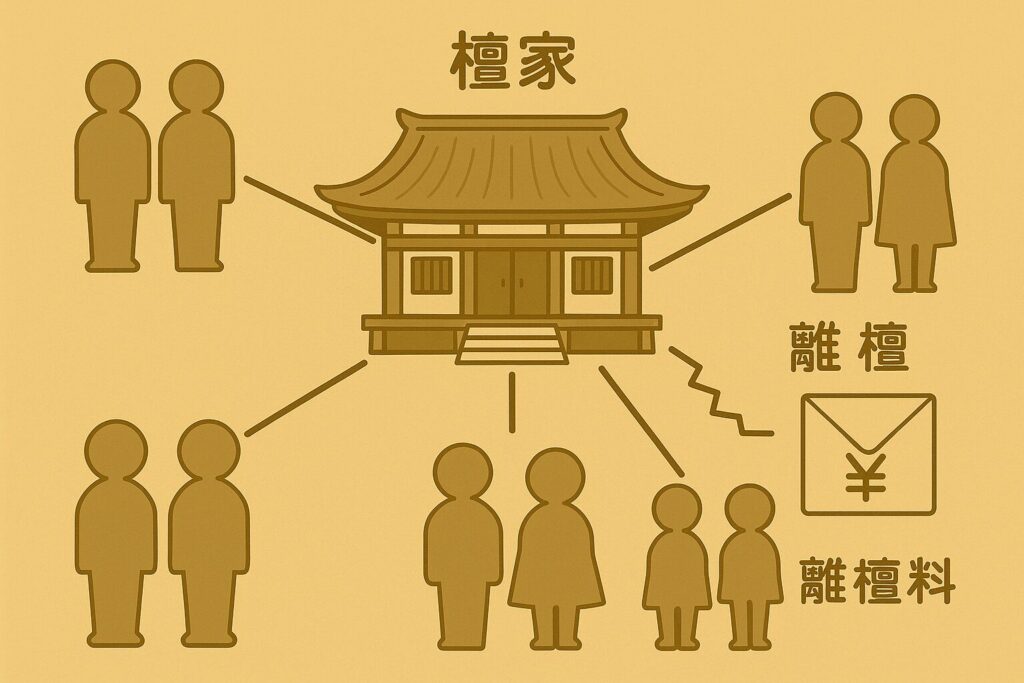
よくある離檀の理由
離檀を考える理由はさまざまですが、主なものとして以下が挙げられます:
- 転居による菩提寺からの遠距離化:引っ越しにより菩提寺から遠く離れ、お墓参りや法事に通うことが困難になった場合
- 継承者不在:少子高齢化や核家族化により、お墓を継ぐ人がいなくなった場合
- 経済的理由:年々の管理費や法要の費用負担が難しくなった場合
こうした事情から、離檀を選択する方が近年増えています。
離檀料の法的位置づけと支払い義務
離檀料は法律で定められた強制的な支払いではありません。墓地使用契約書に離檀料の記載がなければ、法的な支払い義務はないのです。あくまでも「お布施」という位置づけであり、感謝の気持ちを表す習慣です。
ただし、円満に離檀するためには、これまでのお付き合いを考慮して、可能な範囲で支払うことが一般的とされています。
離檀料と混同されやすい費用
離檀に際して発生する費用には以下のようなものがあり、これらが「離檀料」と呼ばれることもあります:
- 閉眼供養のお布施:お墓から魂を抜く儀式の費用(3万円~5万円程度)
- 永代供養への移行費用:取り出した遺骨を寺院で永代供養する場合の費用
これらは本来の離檀料とは別のものですが、一括して「離檀料」と表現されることがあるため注意が必要です。
離檀料の相場はいくらか?
離檀料の相場は、地域や寺院の格によって異なりますが、一般的に3万円から15万円程度とされています。しかし、墓じまいに伴う閉眼供養の費用を含めると、総額で20万円ほどになることもあります。
より具体的には以下のような内訳が考えられます:
- 離檀料のみ:約5万円~20万円
- 閉眼供養と併せる場合:約8万円~30万円
また、遺骨の永代供養をお願いする場合は、以下のような費用が追加されます:
- 永代供養:約10万円~30万円
- 納骨式:約3万円~5万円
ただし、これらはあくまで目安であり、具体的な金額については寺院に事前に確認することが重要です。
墓じまい全体にかかる費用の詳細はこちら
離檀料の地域別・宗派別相場比較
離檀料の相場は地域や宗派により差異がみられます。
関西圏では大阪を中心に5万~30万円が主流で、閉眼供養を含めると8万~30万円に上ります。
九州地方の福岡県では5万~15万円が相場とされ、墓じまい総費用は30万~250万円と広範な幅を持ちます。
宗派別では曹洞宗が10万~20万円、浄土真宗が3万~20万円、真言宗は10万~30万円と傾向が分かれます。
浄土宗寺院では離檀料を定めず気持ち次第とする事例もあり、同一宗派内でも寺院格や地域慣習が費用に影響するようです。
お墓のお手入れと準備に役立つアイテム
離檀や墓じまいの前に、最後のお参りとしてお墓をきれいにしたいという方も多いでしょう。墓石のお掃除には専用のアイテムが便利です。
アズマ社の「墓石清掃アイテム5点セット」は洗剤不要で墓石を優しくケアできます。墓石の溝部分をきれいにするVカットブラシや花立ての奥まで洗えるロングタイプの洗浄具など、専用アイテムが揃っています。
また、お墓参りの際に便利な風よけライターやお線香などをまとめて収納できる「お墓参り3点セット」も便利です。「まとめて保管できるのでお墓参りのときにすぐに持って行くことができる商品で助かります」というレビューもあります。
離檀の手続き方法と必要な準備
離檀を円滑に進めるためには、以下の手順を踏むことをお勧めします:
1. 親族の同意を得る
まず、親族に墓じまいをして離檀したい理由をしっかり伝え、相談して同意を得ておきましょう。先祖代々のお墓に対する思いは人それぞれです。この同意を取らないと、後になって親族間のトラブルになる可能性があります。
2. お寺への相談・交渉
離檀の意思を伝える際は、一方的に通告するのではなく、まずは電話で住職に話をする時間を設けてもらうように予約しましょう。
実際に会った際には、これまでの感謝の気持ちを伝えながら、離檀せざるを得ない事情を丁寧に説明することが大切です。
3. 必要な行政手続き
墓じまいに伴う離檀では、「改葬許可証」が必要になります。
これは遺骨を他の墓地や納骨堂へ移動する際に必要な公的書類です。取得するためには以下の書類が必要です:
- 埋葬証明書:現在の墓地管理者から発行
- 受入証明書:新しい埋葬先から発行
- 改葬許可申請書:市区町村の役所から入手
これらの書類を揃えて市区町村に提出し、改葬許可証を取得します。
4. 遺骨の取り出しとお墓の撤去
必要な許可が下りたら、遺骨を取り出し、墓石を撤去・解体します。これらの作業は専門の業者に依頼することができます。
5. 新しい供養先への納骨
取り出した遺骨を新しい供養先に納骨します。この際、改葬許可証が必要となりますので忘れずに持参しましょう。

離檀料をめぐるトラブルと対処法
離檀時によくあるトラブルとして、「法外な離檀料を請求された」というケースがあります。例えば、100万円や300万円といった明らかに相場を超える金額を請求されることもあるようです。
2024年に5人の遺骨を移す際、寺院から「遺骨1人70万円」と総額350万円を要求された事例が発生しました。
あるケースでは弁護士を交えた交渉で1250万円の請求を50万円まで減額したという報告もあります。
愛知県では300万円の離檀料請求に加え、ローン支払いを迫られる事態も起きています。
主なトラブル要因は「法的根拠のない高額請求」と「改葬手続きの妨害」です。
寺院側が埋葬証明書の発行を拒否し、事実上の離檀料強要に及ぶ例も少なくないようです。
高額な離檀料を請求された場合の対応策
もし高額な離檀料を請求された場合は、以下の対応を検討しましょう:
- 寺院との直接交渉:まずは率直に「その金額は支払えない」と伝え、相場に近い金額で交渉しましょう。
- 檀家総代への相談:寺院の檀家総代に間に入ってもらい調整することも一案です。
- 専門家への相談:行政書士など専門家に相談するのも有効です。
- 宗派本山への相談:寺院が所属する宗派の本山に相談することで解決する場合もあります。
離檀後の新しい供養方法
離檀した後の遺骨の供養方法には様々な選択肢があります。近年は時代に合わせた新しいサービスも登場しています。
永代供養という選択肢
永代供養とは、ご遺族に代わって寺院や霊園が永代にわたって供養や管理を行う仕組みです。一般的な墓地よりも管理の手間がかからず、継承者がいなくても安心です。
料金は施設によって異なりますが、合祀型(他の方の遺骨と一緒に埋葬)の場合、一般的に5万円から150万円程度とされています。
手元供養という新しい形
近年注目されているのが「手元供養」です。これはお骨の一部を自宅で供養する方法で、専用のミニ骨壷や仏具を用いて、いつでも故人を身近に感じることができます。
楽天市場では様々な手元供養用のミニ骨壷が販売されています。九谷焼の美しい色彩の骨壷や、シンプルでおしゃれなデザインの骨壷など、故人の好みや自宅のインテリアに合わせて選べます。
例えば、「虹珠」という手のひらサイズの可愛らしいミニ骨壷は、ピンクやグリーン、白など優しい色合いが特徴で、そっと置いておくだけでも部屋の雰囲気を壊しません。
また、白並骨壷は2寸(直径約6cm)から7寸(直径約21cm)まで様々なサイズがあり、遺骨の量に合わせて選べます。
手元供養に適した仏具セット
手元供養を始める際には、コンパクトな仏具セットもあると便利です。モダンなデザインの「リュシー」シリーズや「ルフラ」シリーズなど、ミニ仏壇に適したコンパクトな仏具セットが人気です。香炉や花立、火立などの基本的な仏具がセットになっており、ご自宅での供養をサポートします。
特に「彩り」シリーズは、橙色や紫色、藍鉄色など様々なカラーバリエーションがあり、インテリアに馴染むデザインが特徴です。
最新の供養サービス
驚くべきことに、ネットを利用して遺骨の永代供養ができるサービスも登場しました。
ただし、こうしたサービスも含め、いずれの永代供養を選ぶ場合も、埋葬許可証または改葬許可証が必要となりますので、事前に市区町村の役所で相談・取得しておく必要があります。
お線香やロウソクのまとめ買いで経済的に
離檀後も自宅での供養を続ける方には、お線香やロウソクのまとめ買いがおすすめです。楽天市場では、マルエス、カメヤマ、日本香堂などの有名メーカーのお線香やロウソクを大量にまとめ買いできるショップがあります。リンク
特に「薫寿堂 特撰花琳」や「玉初堂 香樹林」などの人気商品は、複数箱でのセット購入がお得です。例えば、香樹林の5箱セットは送料無料で単品で購入するよりも経済的です。
ペット用の手元供養グッズ
近年はペットの供養にも注目が集まっています。大切なペットを手元で供養できる専用グッズも充実しています。
「メモリアルBOX」はペット仏壇としても使える12点セットで、おりんやパステルカラーの仏具、骨壷収納スペースなどが揃っています。
また、おうち型のミニ骨壷は、しっとりとした陶器の手触りと優しいパステルカラーが特徴で、写真も納められる設計になっています。
墓じまい代行サービスの利用も検討を
墓じまいと離檀の手続きが煩雑で負担に感じる場合は、墓じまい代行サービスの利用も一つの選択肢です。専門業者に依頼することで、墓じまいに関する一連の手続きをサポートしてもらえます。
墓じまい代行の費用は、業者によって異なりますが、一般的に約15万円~約30万円が相場とされています4。お墓の大きさや立地状況などによって金額は変動します。
まとめ:離檀料と円満な離檀のために
離檀料は、長年お世話になった寺院への感謝の気持ちを表すお布施であり、法的な支払い義務はありません。しかし、円満な離檀のためには、お寺との関係性を考慮し、無理のない範囲でお支払いすることが望ましいでしょう。
離檀の際には以下のポイントを押さえておくことが大切です:
- 事前の親族間での合意:墓じまいと離檀について、親族の理解と同意を得ておく
- 丁寧な交渉:お寺には感謝の気持ちを伝えながら、事情を説明する
- 適切な相場感覚:離檀料の一般的相場(3万円~15万円程度)を知っておく
- 必要書類の準備:改葬許可証など行政手続きに必要な書類を事前に確認する
- 新しい供養先の検討:永代供養など、時代に合った新しい供養方法も視野に入れる
墓じまいや離檀は、先祖代々受け継がれてきたお墓との別れを意味します。感謝の気持ちを持ちながら、丁寧に進めることで、先祖様も納得していただけることでしょう。
お墓の移転や墓じまいについて詳しく知りたい方は、厚生労働省の「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」もご参照ください。
※この記事の情報は2025年4月時点のものです。最新の情報については各自治体や寺院にお問い合わせください。